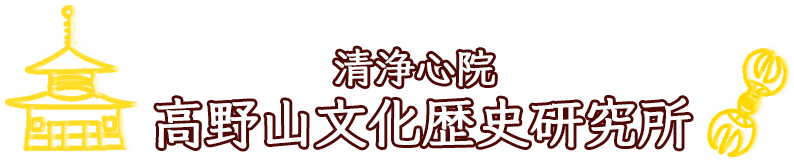高野山奥之院~弘法大師信仰の始まりと広がり -大森龍照 霊宝館長に聞く-

見どころは重要文化財の「奥之院の経塚出土品」と「毘沙門天像」
高野山霊宝館では、令和7年度秋期企画展「高野山奥之院~弘法大師信仰の始まりと広がり~」が開催されています。期間は、令和7年10月11日(土)から令和8年1月12日(月・祝)まで(詳しい日程はこちら)。今回はこの秋期企画展について報告させていただきます。
承和2年(835)、弘法大師空海が高野山の奥之院に入定されて以来、大師を慕う人々の信仰は大師信仰として今日まで連綿と展開されています。特に本企画展では納骨信仰に焦点を当て様々な文化財を紹介されています。この企画展開催を受けて、清浄心院高野山文化歴史研究所の木下が高野山霊宝館長の大森照龍師に“見どころ”となる2つの文化財をお伺いしました。
まず大森館長は、奥之院の御廟近くから発掘された経塚(経典を土中に埋めて盛土したもの)を挙げられました。これは、平安時代後期の12世紀初頭の天永4年(1113)に、「比丘尼法薬」という在俗の出家者が奉納した経典や種字で表された両界曼荼羅です。
通常は紙に記された経典は埋納されても腐食して、ほとんどが形状をとどめていませんが、この経塚は奉納された状態のままに見出されたのでした。それは、経典を納めた容器が、木製・金属製・陶製と三重構造になって納められたからでした。これらは、全て国指定の重要文化財となっています。
次に大森館長が挙げられたのが、高野山内の千手院観音堂に旧在していた、鎌倉時代初頭の大きさが270㎝の毘沙門天像です。この像の胎内からは、大きさが32㎝の小型の毘沙門天像が発見されたのでした。いずれも、国指定の重要文化財となっています。「千手院」は現在の高野山幹部交番近くの信号の東側の広場にあるお堂がそれです。千手院のバス停の語源となっています。仏像そのものを、仏像に奉納する習慣があったことが指摘されます。
本企画展の主な展示物は以下のようです。
| 書跡 | 続宝簡集 | 金剛峯寺 | 国宝 |
| 書跡 | 紺紙金字一切経(荒川経) | 金剛峯寺 | 重要文化財 |
| 彫刻 | 毘沙門天立像(千手院観音堂旧在) | 金剛峯寺 | 重要文化財 |
| 彫刻 | 毘沙門天立像(胎内仏 千手院観音堂旧在) | 金剛峯寺 | 重要文化財 |
| 彫刻 | 不動明王立像(千手院観音堂旧在) | 金剛峯寺 | 重要文化財 |
| 考古 | 金銅宝篋印塔(南保又次郎納骨遺品) | 金剛峯寺 | 重要文化財 |
| 考古 | 高野山奥之院出土品 | 金剛峯寺 | 重要文化財 |
| 民俗 | 高野山奉納小型木製五輪塔及び関連資料 | 円通寺 | 国登録有形民俗文化財 |
| 工芸 | 紺綾地錦弘法大師像 | 金剛峯寺 | 未指定 |
| 工芸 | 紺綾地錦阿弥陀如来像 | 金剛峯寺 | 未指定 |
| 書跡 | 六字名号 | 宝寿院 | 未指定 |
※高野山奥之院出土品=比丘尼法薬経塚出土品・御廟及び周辺出土品・燈籠堂及び周辺出土品。
重要文化財の「金銅製宝篋印塔」(南保又二郎納骨遺品)について
私は、今回の企画展を拝見して、その主な展観品の中でも、金銅製(銅や青銅に金めっきや金箔を施したもの)の宝篋印塔(ほうきょういんとう)を挙げたいと思います。これは総高が27cmと小型ですが完形のもので、金銅製の出来た当時のままに全体が金色に光っています。
宝篋印塔とは、元は宝篋印陀羅尼経(ほうきょういんだらにきょう)という経典を納めた塔のことですが、鎌倉時代には五輪塔に準じて供養塔として多く造立された塔婆でした。金銅製で造られたこと自体も、大変珍しいことが指摘されます。
また、本宝篋印塔で注目されるのが基礎の四面に刻された銘文です。「大師御入定奥院埋土中、安置高野山八葉峯上、南保又二郎入道遺骨也、弘安十年六月二十二日卒」とあります。銘文は、鎌倉時代の弘安10年(1287)6月22日に没した「南保又二郎(なんぽまたじろう)」の遺骨を本宝篋印塔に納めて、高野山奥之院の御廟近くに埋納したことを記しています。
これまでの研究では南保又二郎が一体どのような人物なのか分かっていませんでした。ところが、『源平盛衰記』(げんぺいせいすいき)という鎌倉時代始めに成立した源氏と平氏の騒乱の様子を記した文献の中で、「南保次郎家隆」という人物がいたことを見出すことが出来ました。寿永2年(1183)「安宅・篠原合戦」において木曾義仲軍に従った越中国の武士の中の一人として描かれています。
『源平盛衰記』に出る「南保次郎家隆」と、金銅製宝篋印塔の銘文にある「南保又郎」は同系の人物ではなかったかと推測します。中世の武士においては通り名(とおりな)として、一家の主人が先祖から代々受け継いで用いる同一の名の同名を名乗るケースがあります。金銅製宝篋印塔に名前がある南保又二郎(なんぽまたじろう)は『源平盛衰記』に記載の越中国の武士の南保次郎家隆(なんぽじろういえたか)の後胤の人物ではないかと推測します。
高野山奥之院には、戦国時代の武将の石塔が群立していますが、鎌倉幕府の御家人と言われた武将も、金色に光る供養塔を造立しているのです。高野山からは、遠く北陸から造立されたものです。
この金属製の宝篋印塔は国指定の重要文化財です。金色に輝く本塔は、造立当時のままに光り輝いています。この機会に是非ともご覧いただくことをお勧めします。
清浄心院高野山文化歴史研究所 所長 木下浩良